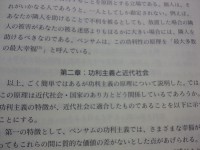社会福祉士レポート実例(心理学基礎実験-設題2)
社会福祉士のレポート作成にお悩みの方へ
実際のレポート作成例をここに提示します。
この科目は、社会福祉士と同時に、認定心理士のコースをとっている学生ならば必修の科目となっております。
心理学の実験法を学ぶ専門的科目で、比較的難易度の高い科目の一つです。
ポイント(学習ガイドより)
近未来において人間が直面しうる社会的・心理的問題について、実験心理学が応用面から対応していくことが期待されている。さまざまな方面で今後予想される問題と、それに対する実験心理学的対応の可能性や方向性について具体的な例を挙げて説明すること。また、テキストや参考書から理解した内容や具体例だけでなく、自分自身の視点や問題意識を踏まえた例や考えを含めて考察すること。
設題2
「実験心理学と日常生活・社会との関連について、あなた独自の視点や考えを加えながら論じなさい。」
現代は、変化の速い時代だと言われており、企業はリストラを余儀なくされている。そんな中で、終身雇用制度は徐々になくなり、能力のある人材だけが、生き残れる時代になろうとしている。そのような状況の中で、企業における重要な課題は、人材の管理(マネジメント)であろう。
そこで実験心理学が、人材を管理するうえで、どのような対応ができるのかという疑問が生じた。本設題では、実験心理学が企業の人材管理にどう対応できるのかを、日常生活・社会との関連において考察し、近未来における日本においてのコミュニケーション方法と実験心理学について考察する。
ここでは、まず企業の管理者と呼ばれる立場の人が、部下をどのように指導しているかについての例を示し、それがどのような結果をもたらしているのかをまとめる。
企業における管理者の意見でよくあるのが「部下が言うことをきかない」「部下は仕事に対する意欲がない」という類いのものである。要するに部下が自分の指示した通りに仕事をしないという意見である。
このような意見を持つ管理者に共通するものは一体何であろうか。それは「デレゲーション-delegation-権限委譲」(以下、dlgと表記)という用語によって説明できる。dlgとは「ほかの人に仕事を任せる⑴」という意味で、多くの管理者には、dlgの概念がない。つまり仕事を指示するときに「あれを取ってこい」「これをとってこい」「ああしろ・こうしろ」という指示の仕方をしている。このような部下の管理の仕方を、dlgではないという意味で「非デレゲーション」(以下、非dlgと表記)と呼ぶことにする。管理者が非dlgになりがちな理由としては「部下を信用していない」とか「dlgの方法が分からない」ことが挙げられる。
このような管理者に指導されている部下が、どのような人材になるかというと、いわゆる「指示待ち人間」である。指示されなければ動かないのみならず、指示された以上のこともしない・できないタイプの部下といえる。
次に、この問題に対して実験心理学は、どのような対応ができるのかを考えてみる。それは、企業の管理者を対象にしたdlgの研修会を実施するということである。管理者を集め、実験を通して、実際に dlgと、非dlgの違いを体験してもらい、それを今後の仕事に活用してもらうのが目的である。どのような実験方法が考えられるかを具体例として次に示す。
まず、異なった企業から管理者数人を集め、Aグループ(実験群)とBグループ(統制群)に分ける。ここでは違う企業の同業種の生産業から被験者が選ばれる。そこで一つの課題が与えられる。その課題を自分の部下を使って果たさなければならない。Aグループはdlgの方法を用いて課題をこなし、Bグループは、非dlgの方法で課題をこなすこととする。
課題は「1週間以内に仕事の生産性を前週よりも 20%上げる」というものである。
実験にあたって、Aグループには以下の原則を守ってもらう。それは「結果を達成できれば良く、その手段は部下に選択権があることを伝え、管理者は直接手を下さない」ということである(本来のdlgは管理者が何もしないことではないが、実験ではあえて何もしないものとする )。
一方、Bグループは、望む結果を達成するための手段はすべて管理者が決定し、部下はただそれを実行するだけの形で課題に取り組むことにする。
以上の方法によって実験を行う。その結果として課題を達成できるのは、Aグループである確率が高い。それは「課題を達成するための選択権が部下に渡されたことで、信頼されれたという動機づけが発生し、課題に対する達成意欲が強くなった
この実験においては、A・Bは両グループでの条件が統制されていないという反論があるかもしれないが、特にそれは問題ないと考えられる。
その根拠は「ホーソン実験」にある。これは「アメリカのウエスタン・エレクトリック社のホーソン工場で行われた、物理的労働環境を整備することにより、従業員の疲労を軽減し、生産性を上げるために行われた実験のことである。照明度と作業能率の相関関係や、従業員の休憩時間や労働日数などの変化を通して生産性の変化を明らかにしようとしたが、結果は、照明・休憩時間・労働日数などの物理的、物質的労働条件は生産性とは関係がないと結論づけられている ⑶」。
以上の実験を通して、管理者は部下に対する管理法を体験してもらう訳だが、この手法は、日常生活にも応用できるものである。例えば親が子供に、ある課題を達成させようとする時がその典型で、dlgを用いれば効果的なマネジメントが可能である。
このdlgの実験は、AグループとBグループの差を検証するために行われるものである。したがって実際のdlgにおいて管理者は、部下に仕事を任せたことで、それ以外の、より重要な仕事に取り組まなければならないことは、補足として付け加えておく。
近未来の日本では、人口減少がさらに深刻化し、将来的には海外の移民を受け入れるという状況も予測される。つまり日本は、今までの 一民族国家から、多民族のグローバルな国際社会へと進展していくことが十分に考えられる。そのとき、重要とされるのはdlgを始めとするコミュニケーションの方法である。企業における管理者は「なぜこれをするのか」「どういう理由で行うのか」を説明し正当化する説明責任を果たすことに求められる。
これからはdlgのような新しいコミュニケーション方法が必要とされる時代がくる。そういう意味で実験心理学は、近未来の日本において欠かせない学問分野になるといえる。
【後注】
⑴スティーブン・R・コヴィー243頁参考
⑵ティーブン・R・コヴィー256頁参考
⑶山岸俊男 30~31頁参考
【参考文献】
- スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』キング・ベア出版 1996年
- 山岸俊男『社会心理学キーワード』有斐閣 2001年
■■レポート通信課題を書くときのコツと起こりうる現象■■
このレポートは、心理学の専門書を使って書いたのではありません。
主に参考にした書籍は『 7つの習慣』というベストセラーのビジネス書です。
今回のレポートは、心理学のレポートがビジネス書を参考文献にしたとしても書けるということを示した例になります。
レポート書く前の段階で、設題には「あなた独自の視点や考えを加えながら論じなさい」と示してあったので、何かいいアイデアはないかなあと悩んでいました。
そして思いついたのが、デレゲーションのアイデアです。
私は、昔からビジネス書をよく読んでいたので『7つの習慣』の内容は、よく知っていました。
なので「これだ」ってひらめいたんです。
デレゲーションは、第三の習慣である「重要事項を優先する」の章の中で紹介された話です。
レポートの中では、字数制限の関係で、詳細を詳しく述べることはできませんでした。
レポート本文には、
デレゲーションと、非デレゲーションがあり、これらを実験群と統制群に分け・・・・・
といった感じで、さらっと説明するに留まっています。
しかし、心理実験のレポートで重要なのは、なぜそれ取り上げるのか、そしてそれをどうやって実験に結びつけるかです。
本編『七つの習慣』の中では「完全なデレゲーション」と「使い走りのデレゲーション」という対比で詳細に解説されています。
完全なデレゲーションは、信頼関係の構築を基礎とし、結果を出すにあたってのガイドラインが明確で、能率ではなく、効果を目指す人間関係重視の方法です。望む結果を得るために、相手の自覚・想像力・良心・自由意志を尊重する方法です。
デレゲーションを支持する心理学の実験は何かないかと探して、やっと見つけたのが、この「ホーソン実験」でした。
ホーソン実験は、労働者の作業効率が、単に照明の明るさなどの労働環境によって変化するのではなく、その職場の人間関係やリーダーのあり方などに影響を受けることを提起した実験です。
実験に対する評価は、賛否両論あるものの、ともかくも
ホーソン実験の結果は、デレゲーションを支持するものだったのです
またしても「これだっ」ってひらめきました。
デレゲーションという言葉は、心理学の専門用語ではないのですが、企業の管理者が部下に与える影響力という観点に着目し、それをもとに心理実験のアイデアを思いついて、レポートに書くことにしました。
もちろん、こうした心理実験を思いついたとしても、実際に実験できるわけではないので、実験の結果に関しては本当の研究論文のような科学的なものとはいえないでしょう。
しかし、ホーソン実験という心理学の実験を根拠として持ち出し、説得力を出し、理論を展開しようと試みています。
実験の記述自体は想像なわけですが、その記述のもとになっているのは、教科書から学んだ実験心理学の専門的知識です。
実験をしない、もしくはできないといっても、その前提となる用語は押さえる必要があります。
押さえるべき用語は
- 実験群や統制群
- 独立変数と従属変数・剰余変数
- 1要因実験と多要因実験
- 被験者内変数と被験者間変数
となります。
レポートで書こうとする実験例に合わせてこれらの用語を使いこなすことが教員に対する学習成果のアピールになりますので、教科書をよく読むことは、実験の基礎を押さえることになり、地味でありながら着実な単位習得への道でもあります。
逆に言えば、実験の基礎を抑えれば、あとは独創的なアイデアが高評価のカギです。
レポートは、設題のみならず、その科目ごとのポイントを押さえることが必要です。
そのポイント読んでみてですが
かなり独創的で自由な発想のレポートを求めているなと感じました。
これは私の、ファーストインプレッションです。
あなたにお勧めしたいのは、レポートを書くときは、こうしたファーストインプレッションを忘れないようにメモなどに記録しておくことです。
そうすることでいろいろなアイデアが思いつくことがあります。
最初に感じたことが、結局は最後の結論になることもあります。
あるいは、実験のアイデアが思い浮かぶこともあります。
今回のレポートがまさにこれに該当しました。
つまり、後で思い出そうとしても思い出せないことは多々あるので、感じたことはメモしておくことが独創的なアイデアを生み出すコツといえます。
これは、他の科目のレポートにおいても使えるコツです。
最後に、レポートの書き方における現象を一つお伝えします
それは、
レポートの書き方は教員によって微妙に異なる
という事実です。
当初、このレポートでは、次のように、章こどに項目を立てて書いていました。第2章:実験心理学の対応
という部分です。
それと、実験の記述部分のパラグラフには
実 験
という項目を立て、
最後のまとめのところでは、
結 論
という書き方をしました。
こんな感じです。
赤ペンで添削してありますが、これは、書く必要はないですよという意味です。
実は、こういう書き方をしたのは、私が参考にしていた、この書籍に習ったからです。
『レポート・論文の書き方入門』河野哲也 著
私が書いたレポートは、この書籍に少なからず影響を受けています。
レポートの添削部分をみる限り、私の書いたレポートを添削した教員と、河野先生は、レポートの書き方について意見の相違があるようです。
河野先生の見本レポートによると
御覧のように、パラグラフこどに、第○○章といった書き方をしています。
書き始めには
序
という文字があります。それと最後には、
結 論
という書き方もしています。
要するに、レポートの書き方は、人によって違うというのがお分かりいただけたでしょうか?
『レポート・論文の書き方入門』を執筆した方は、専門が哲学です。
今回、私のレポートを添削した方の専門は、心理学です。
専門が異なると、レポートの書き方も微妙に異なることがあります。
また、学会が定めた引用のルールも存在します。
なのでこうした現象が起こるということになります。
もちろん、文章によっては、専門に関わらず、項目を立てた方がよいという場合もありますが、今回のような書き方の場合は、項目を立てる必要はないということは分かりました。
レポートを添削する教員は、その辺の事情は、やはりプロですのでわかっているようで、こうした些末なことで減点をしてくることは少ないというのが、私の確認した事実です。